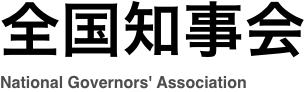先進政策バンク詳細ページ
| タイトル | 環境問題を楽しく学習 走れエコムーブ号! |
|---|---|
| 施策・事業名称 | 動く環境教室(エコムーブ号)の運営 |
| 都道府県名 | 群馬県 |
| 分野 | 環境 |
| 事業実施期間 | 平成14年4月1日~ |
| 施策のポイント |
・学校等で行われる環境学習を応援するため、移動環境学習車「エコムーブ号」による「動く環境教室」を実施。 ・県に登録した環境学習サポーターが直接学校等に出向く。 ・8つのプログラムから2つを選択し、2校時を使って受講。 ・年間、約5,000人のこどもたちが利用。 |
| 内容 |
<背景・経緯> 今日、自然と共生した持続可能な社会の形成が求められています。そのためには、一人一人が「人と環境」の関係について学び、行動に移すことが必要です。 特に、こどもの頃から環境について考えてもらうため、こども向けの環境教育を充実させることは、今後の持続可能な社会の実現に向け非常に重要となっています。 <目的・ねらい> 環境学習では、体験を通して守るべき自然への理解を深め、科学的思考力と体験を通した総合的な理解力を深めることが重要です。こどもの頃からこうした思考を身につけることにより、環境保全に対する自らの責任と役割を自覚し、進んで環境保全行動に参加する意欲を持ち、問題を解決するための能力を高めていくことが期待されます。 <事業の概要> 県内小中学校からの要望に応じて、展示品や実験機材を搭載した車両である「エコムーブ号」及び実際に授業を行うボランティアである「環境学習サポーター」を派遣します。 具体的な学習内容としては、下記の8つのプログラムから2つを学校に選んでもらい、2校時を使って授業を行っています。 ◆実施している8つのプログラム (1)家庭から出る水の汚れを調べる → 水質簡易検査(COD)比較 (2)川や池の水質を調べる → 水質簡易検査(COD、DO等) (3)自動車排ガスの汚れを調べる → ザルツマン試薬による比較等 (4)ごみは大切な資源→ごみ分別ゲーム(3Rの確認等) (5)サイクルについて考える → ペットボトルから繊維作成等 (6)電球から地球温暖化を調べる → ワットアワーメーター光源比較 (7)発電から地球温暖化を調べる → 自然エネルギー、燃料電池発電 (8)SDGsの基本について学ぶ→SDGsかるた(SDGsの目標を学ぶ) 環境学習サポーターは、本県の「環境アドバイザー」に登録している方を中心に希望を募り、研修を実施した上で学校に派遣をしています(令和4年度末現在で34人)。 また、地域における環境活動やボランティアの中核となる人材を育成することを目的とした「エコカレッジ(ぐんま環境学校)」事業の中でも、動く環境教室に関する講座を設け、環境学習サポーターの研修を実施しています。 <実績・効果> 統計を取り始めた平成17年度から令和4年度までの18年間に延べで、約9万人(市町村イベントへの出展も含む)が受講しています。 ◆過去5年の受講者(実施回数) ・令和 4年度 3,425人(73回) ・令和 3年度 2,309人(45回) ・令和 2年度 3,182人(59回) ・令和元年度 7,131人(94回) ・平成30年度 5,383人(87回) 学校の先生からは、「普段学校の授業ではできない実験などをやってもらい、こども達も良い体験ができたと思う」、「難しい内容を、実験や体験を通してわかりやすく指導してもらった」など、授業を受けたこども達からも、「電球よりもLEDの方が消費電力が少ないことがよく分かった。家でもできるだけ多く使ってみたい」、「ペットボトルだけでなくいろいろリサイクルをしていきたい」などの感想をいただいており、学校での環境学習の広がりや、家族で環境問題を考えるきっかけとなっています。 <今後の取組> 平成30年度に車両の更新を行ったことにより、これまで出向くことのできなかった県北部及び西部の学校での授業実施が可能となったことから、これらの地域の教育委員会を通じ、事業のPRを行うともに、低学年や幼児用のプログラムを開発し、年齢に応じた環境学習を体系的に実施します。 また、令和4年度よりパソコンとプロジェクターを導入することにより、これまでパネルや手持ちの資料等で提示していた教材のデジタル化を図り、より児童・生徒にわかりやすい教材提示を行います。     |
|
関連 ホームページ |
https://www.ecogunma.jp/?p=46 |
| 本件問合先 | 環境森林部環境政策課 |
| 027-226-2821 | |
| ecosusumu@pref.gunma.lg.jp |