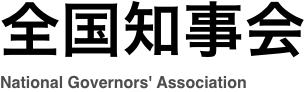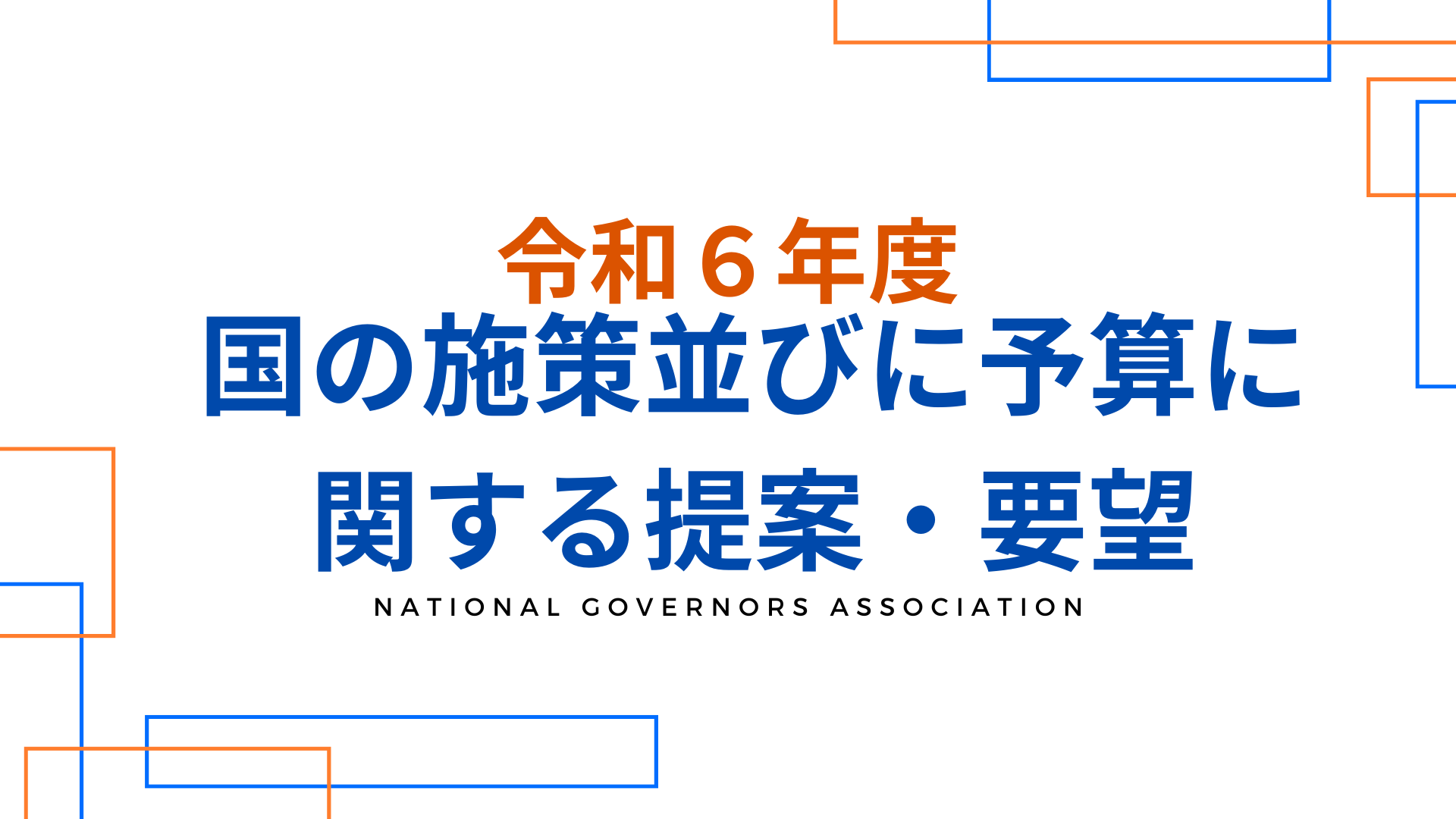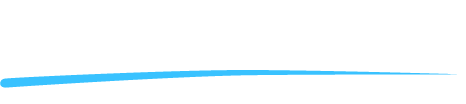
新着情報
- 令和6年04月19日委員会・本部 「令和6年度第1回総合戦略特別委員会」の開催について
- 令和6年04月10日委員会・本部「令和6年度第1回地方分権推進特別委員会」の開催について
- 令和6年04月08日委員会・本部ライドシェアに関する意見交換会について
- 令和6年04月02日声明・メッセージ北朝鮮ミサイル発射に対する抗議声明について
- 令和6年03月29日危機管理・防災令和6年度における東日本大震災に係る福島県への職員派遣について
- 令和6年03月28日危機管理・防災令和6年度における大規模災害に係る復旧・復興対策のための職員派遣について
- 令和6年03月18日声明・メッセージ 北朝鮮ミサイル発射に対する抗議声明について
- 令和6年03月15日声明・メッセージ第十四次地方分権一括法案の閣議決定について
- 令和6年03月01日委員会・本部子ども・子育て政策推進本部意見交換会(第2回)の開催について
- 令和6年03月01日声明・メッセージ地方自治法改正案の閣議決定を受けて
- 令和6年02月08日委員会・本部全国若手町村長会のミーティングで「休み方改革」を説明しました
- 令和6年02月07日その他令和6年北方領土返還要求全国大会について
お知らせ
-
現在、お知らせはございません