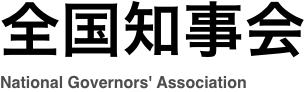先進政策バンク詳細ページ
| タイトル | 犬と猫の処分頭数を減らしてヒトと動物が共生できる社会へ! |
|---|---|
| 施策・事業名称 | 犬猫の処分頭数削減事業 |
| 都道府県名 | 岡山県 |
| 分野 | 健康福祉 |
| 事業実施期間 | 平成25年4月1日~ |
| 施策のポイント | 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)が改正され、犬又は猫の引取り要件の厳格化や譲渡事業の推進などが明記されたことを受け、犬・猫の処分頭数の削減に取り組むことで、ヒトと動物の共生できる社会を構築する。 |
| 内容 |
1.背景 岡山県(岡山市及び倉敷市を除く)では、動物愛護センター(以下「センター」という。)開所前の平成16年度には、犬猫合わせて4千頭弱を処分しており、その後、少しずつ減少したが、平成24年度でも2千頭弱処分していた。そのため、いかにこの処分頭数を削減するかが、動物愛護行政において、重要な課題となっていた。 2.事業内容 (1)引取り頭数削減のための取組 平成25年施行の改正動物愛護管理法により、犬猫の引取り要件の厳格化が明記され、相当な事由がないと認められる場合は引取りを拒否できることになった。これに基づき、飼育している犬猫の引取りを求められた場合は、センター職員がその理由を聴取し、終生飼養をするよう理解を求めている。 また、安易な引取りを防ぐため、保健所及び支所において行っていた引取り業務を除々に削減し、平成27年度からはセンターのみでの引取りとしている。 (2)元の飼い主への返還に向けた活動 保護された犬・猫については市町村への通知や動物の保護収容情報をホームページに迅速に掲載し、市町村や警察等と連携して所有者への返還に努めている。 (3)譲渡事業の推進 センターでは、収容された犬・猫の健康管理に心がけ、簡易な治療や、ワクチン接種、不妊措置等を施し、少しでも譲渡できるように努めている。また、できる限り生存の機会を与えるために、様々な形の譲渡事業を行っている。 1一般譲渡 センターが実施する審査に合格した犬猫について、譲渡会を定期的に開催し、希望者に譲渡する。 譲受希望者には、犬・猫の飼い方講習会(譲渡講習会)の受講を義務づけ、適正飼養や法令に関する知識の習得を図っている。 2団体譲渡 1に適さない犬猫については、施設などに係るセンターの審査基準をクリアするとともに、面談により適切と判断し、登録を受けたボランティア(団体又は個人)に対して譲渡を行い、新しい飼い主を探してもらっている。なお、犬猫の譲渡に際して、登録ボランティアとコミュニケーションを図り、双方の良好な関係の構築に努めている。 3特別譲渡 1及び2において譲渡されなかった犬猫について、動物愛護センターHPに掲載し、希望者に譲渡を行っている。譲渡希望者には、譲渡講習会の受講を義務づけている。 4団体特別譲渡 1~3で譲渡に至らなかった犬猫について、特別団体譲渡ボランティア登録を受けた団体に譲渡している。 (4)普及啓発活動 センターに収容される犬猫を減らすため、飼い主に対し、法の順守、終生飼養、繁殖制限措置、迷子にならないための所有者明示措置など、適正飼養の徹底について、以下のとおり、啓発事業を行っている。 ・ホームページ、テレビ、ラジオ、新聞等マスメディアを利用した広報活動 ・動物愛護週間街頭キャンペーン ・動物愛護フェスティバルの開催 ・飼い方講習会の実施 ・しつけ方講習会の実施 ・動物ふれあい教室の実施 ・愛犬里帰り交流会の開催 3.取組の効果 犬猫の引取り頭数は、引取り要件の厳格化の順守等により大幅に減少し、返還については、犬の返還率が大きく向上した。また、譲渡頭数については、犬猫合わせた譲渡率が、平成24年度の 11.4%から平成30年度の80.9%に上昇した。保護収容頭数は、動物愛護の普及啓発等により平成30年度は平成24年度のおよそ半数となった。(表) これらの取り組みにより、犬猫の処分頭数は、平成24年度は1,829頭(犬610頭、猫1,219頭)であったのが、平成30年度には24頭(犬5頭、猫19頭)となり、大幅な削減ができた。 負傷等により処分された個体を除いた犬猫の殺処分数について、平成29年度、都道府県別(政令市及び中核市を除く)で全国トップであり、ヒトと動物が共生する社会を目指すために非常に効果があった。 4.今後の方向性 犬の放し飼いの減少や猫の室内飼いの増加等、犬猫の飼い主の意識は年々向上しているが、いまだに、子猫の遺棄は絶えず、野犬、野良猫に関する苦情も年間千件以上あり、収容頭数も年間500頭前後で推移している。 また、譲渡率は上昇したものの、団体譲渡が約75%を占め、センターに登録されている愛護団体の協力に頼っている状況である。 これらのことから、適正飼養や終生飼養についての普及啓発等、保護収容頭数の減少にむけた対策が必要である。 今後は、従来の事業を継続していくことはもとより、多頭飼育者の把握とその崩壊の防止、野犬対策、遺棄の撲滅等の課題に取り組む必要があり、まずは、子猫の遺棄対策も含め、飼い主のいない猫による苦情削減に向けた、地域猫活動支援事業から取り組んでいく。  |
|
関連 ホームページ |
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/191/ |
| 本件問合先 | 岡山県保健福祉部生活衛生課 |
| 086-226-7338 | |
| eisei@pref.okayama.lg.jp |